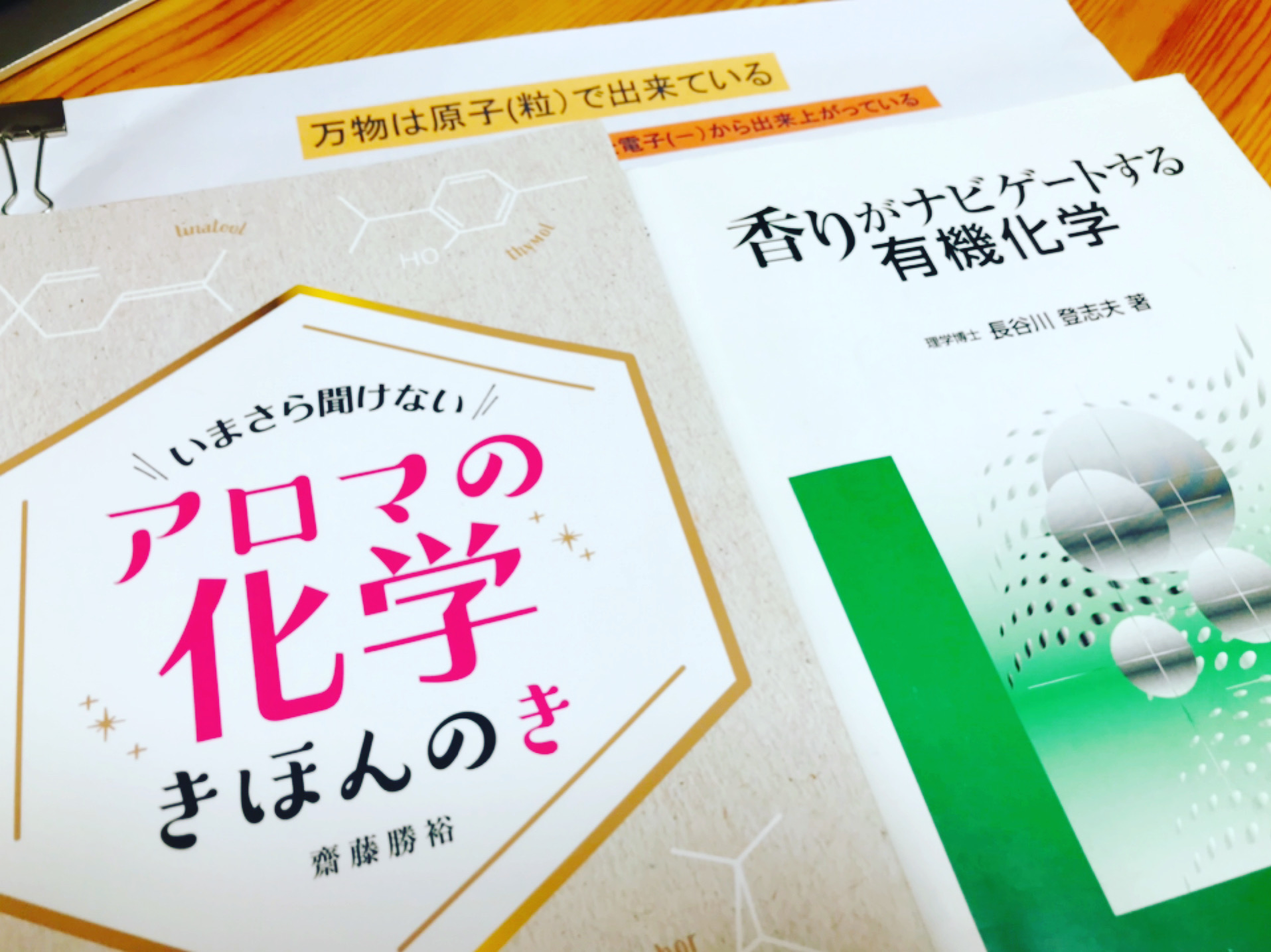昨日は久しぶりに対面でのレッスンを受講してきました。
朝10時〜18時までガッツリ学んできたのは「化学の基礎」です。「精油の化学」じゃないんですよ〜。
精油の化学を知るために必要な基礎の部分です。
中学・高校の化学の学び直しです。
「精油の化学」の部分でちょっとあやふやな部分があったのですが基礎を知って納得しました。
基礎、土台って本当に大切だなと痛感しました。
基礎を丁寧に学んで理解すれば大抵のことはわかってきます。
私たちアロマの世界の人間の化学の学びは、基礎を飛ばしていきなり応用の部分から入ってしまうので、
なぜそうなのか?が抜け落ちてしまっているんだと思うのです。
精油の芳香分子名を暗記して作用を暗記して・・・というのはあまり役に立たないものです。
香りのある物質、芳香分子の構造式から何がわかるのか?を知ることが、
安全に精油を使うことに繋がっていくと思うのです。
そのためには化学の基礎の部分、原子とは?分子とは?から丁寧に知ることが必要だと思いました。
irodoriでお伝えしている「精油の化学」でも、原子とは分子とは?からお伝えしています。
この部分、今回のレッスンを受講したことで、もう少し厚みのあるお話ができると思っています。
なぜ「化学」を学ぶのか。
それは精油を安全に使うために必要だからです。
例えばベンゼン環を持つ芳香分子がなぜ毒性が強いと言われるのか。
例えば二重結合を持つ芳香分子が反応性が高いと言われるのか。
その理由がわかれば、こんな使い方だと安全だけれどこんな使い方だと危険ですよ、
ということが伝えやすくなります。
安全な精油の使い方を伝えるためにも「精油の化学」の部分は知っておいて欲しいところです。
ただし、精油の化学を知っていれば全てかわかるわけではないのが精油の世界です。
偏ることなく多方面から精油を眺めることが大切です。
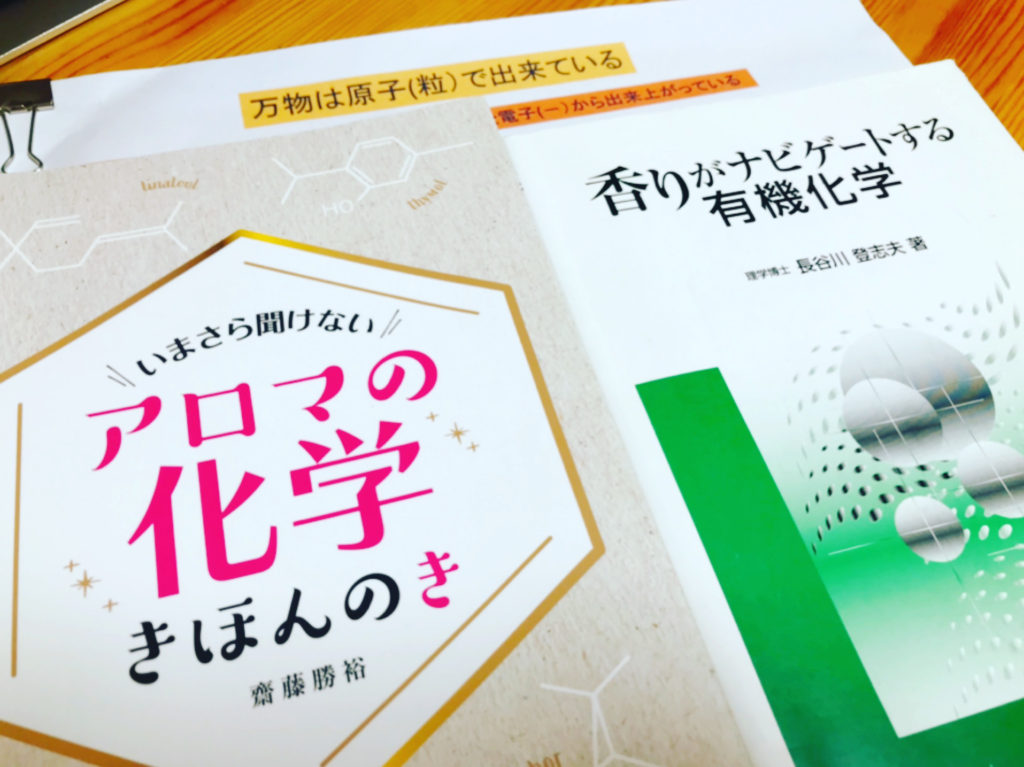
右側の本ですが「香りがナビゲートする〜」という言葉に惹かれて購入したのですが、
あまりの難しさに読めずにいました。
ですが。
今回化学の基礎を受講したことで、この本の内容が少しわかるようになったんですよね。
ということでやはり基礎はとっても大事ですね。
「精油の化学・基礎講座」はリクエストにより開催いたします。
ご希望の方は「お問い合わせフォーム」よりご連絡くださいませ。
こちらの講座はスクール開校当初よりお届けしているレッスンですが、
何度も内容を見直し構築しなおしているレッスンです。
常に「ここは知っておいた方が良いのではないか?」という目線で改良していますので、
必ずお役に立てる内容だと思っています。
オンラインでの受講も可能です。